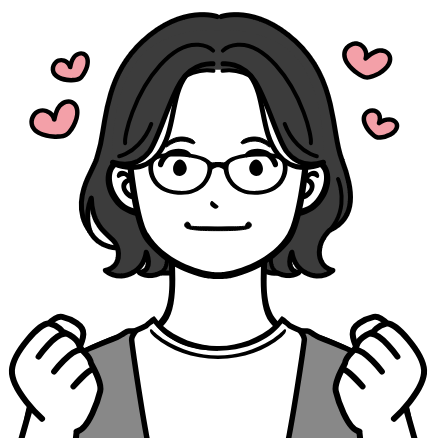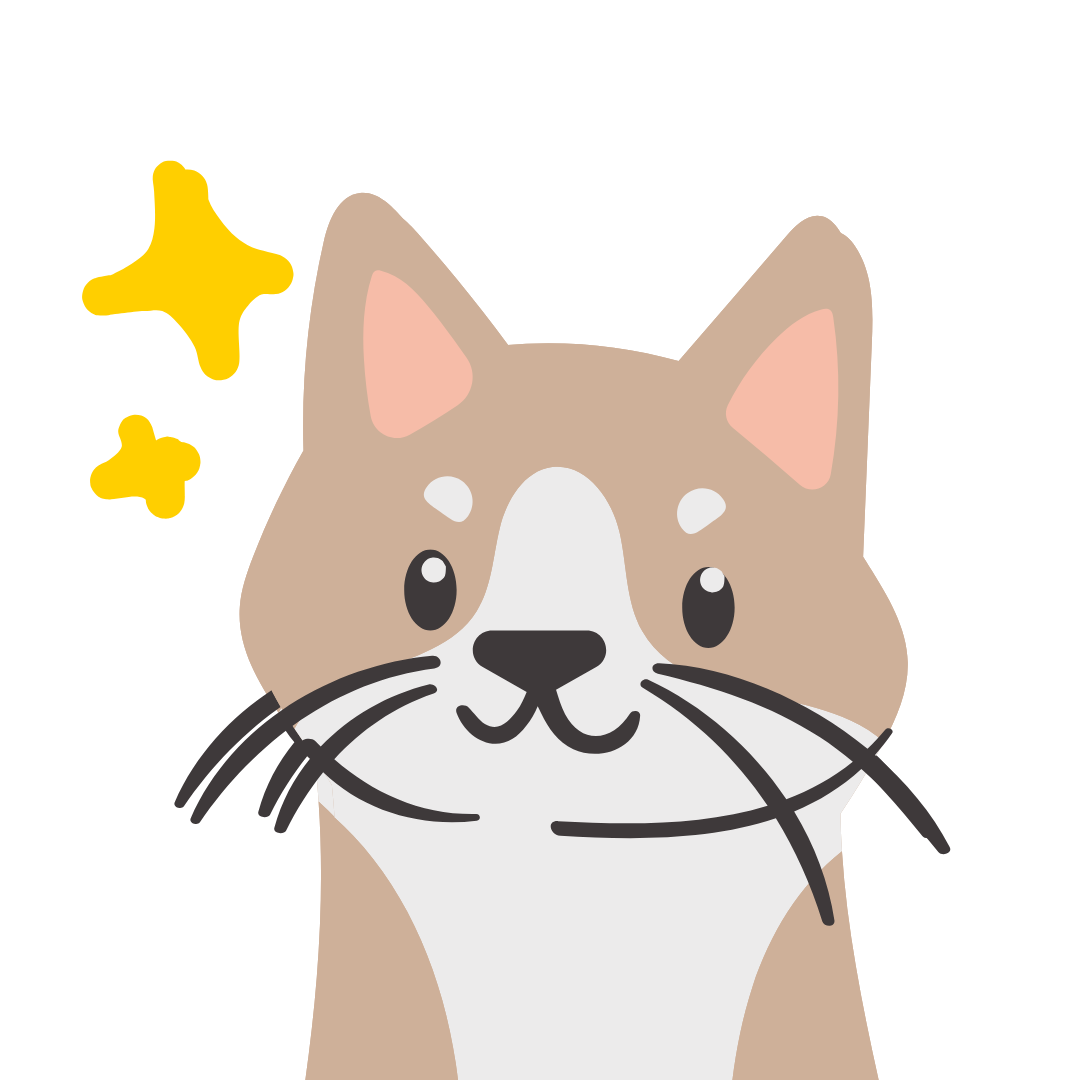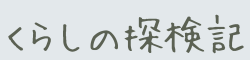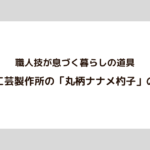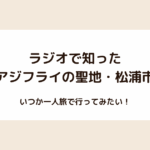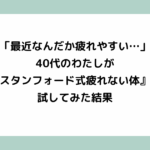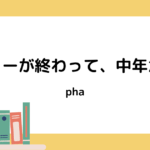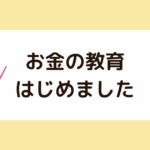わたしは韓国ドラマ好きなんですが、見ていて、いつも気になっていたものがあります。
それは、リビングの棚にずらりと並ぶ薬膳酒の瓶たち。
朝鮮人参をはじめとした漢方素材が焼酎に漬けられ、特別な日の一杯として大切にふるまわれる――そんなシーン、見たことありませんか?
お客さんに出すときも、「これはとても貴重なお酒で、体にいいんだからね」と笑顔で差し出すあの光景。
医食同源の考えが今でも暮らしの中に息づいていることがよくわかります。
そんな素敵な文化に触発されて、わたしも「薬膳酒づくり」に挑戦してみました!
この記事のもくじ
薬膳酒づくりの参考にした本
薬膳酒に興味はあっても、難しそうな材料や工程にハードルを感じている方も多いはず。
そんな人の強い味方なのが、今回参考にした『未病を治す薬膳酒』。
この本の魅力はなんといっても、スーパーで手に入る食材だけで作れるところ!
写真が多く、解説も丁寧なので、初心者にもとてもわかりやすいです。
今のわたしの悩みに合う薬膳酒は?
最近、こんな体の変化を感じていました。
- なんとなく元気がない
- 足腰が弱ってきた
- 白髪が増えてきた
本を読みながら、「今のわたしに合いそう!」と選んだのが、黒ごま酒です。
黒ごまの効能とは?
黒ごまは料理ではちょっとした脇役的存在ですよね。
でも実は、健康や美容の面ですごいポテンシャルを秘めた食材なんです。
黒ごまの主な栄養素・働き
- ゴマリグナン(セサミンなど):強い抗酸化力
- ビタミンB群、E
- カルシウム、鉄、亜鉛などのミネラル類
これらにより以下のような効果が期待できます。
- 動脈硬化・高血圧の予防
- 肝機能の強化
- アルコール分解の促進
- 美肌・代謝の向上
さらに東洋医学では…
滋補肝腎・養血益精(じほかんじん・ようけつえきせい)
体に栄養を与え、血や精を補ってくれる作用があり、
- 疲れやすい
- 白髪が気になる
- 微熱
- 耳鳴り
- 目のかすみ
などの症状改善に。
潤燥滑腸(じゅんそうかっちょう)
腸を潤して便通を整え、乾燥肌や便秘の改善にも効果が期待できるそうです。
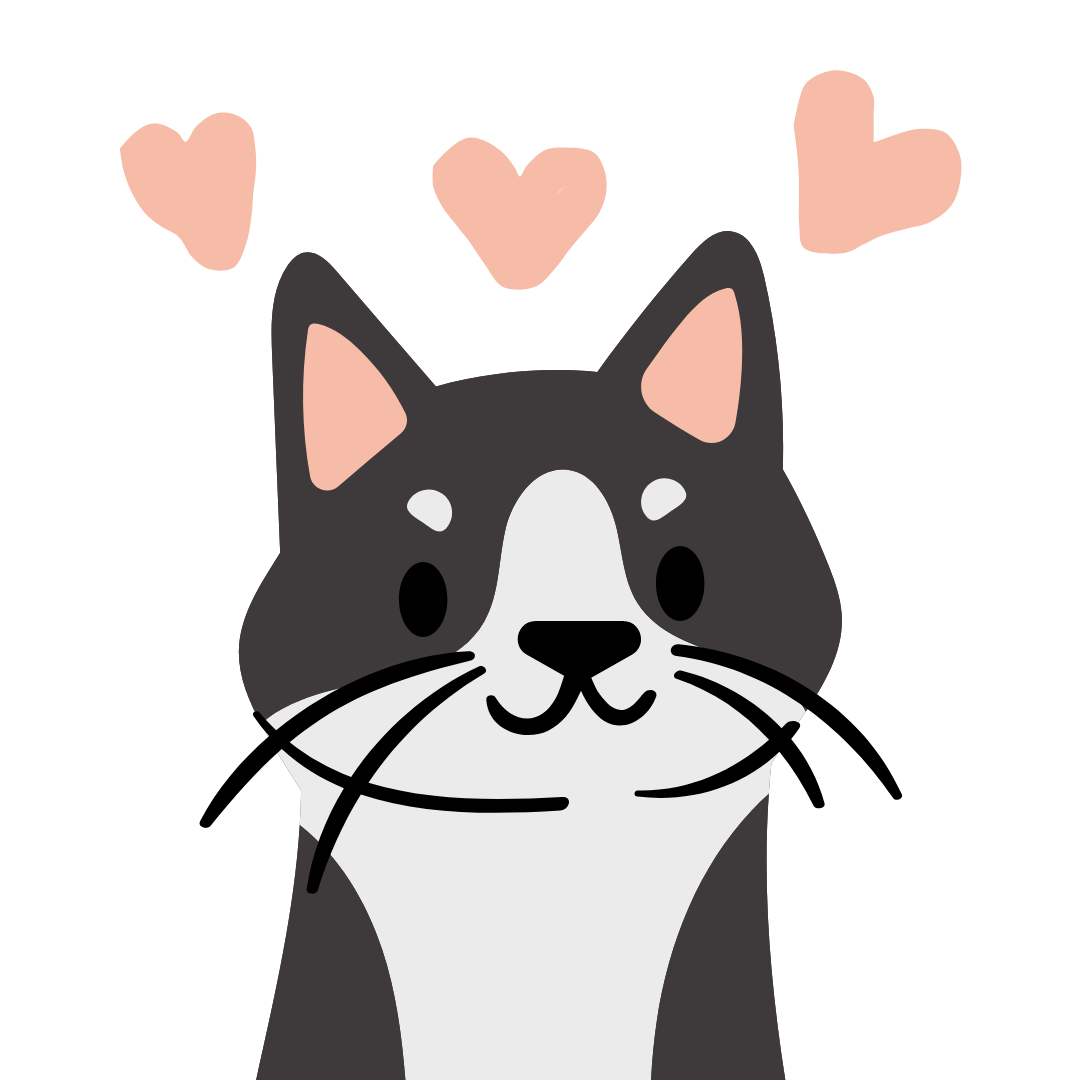
黒ごま酒の作り方
黒ごまの効果がわかったところで、薬膳酒づくりに取りかかっていきましょう。
今回はお試しなので、少量でつくっていきます。
材料
- 黒ごま 40g
- 焼酎(25度) 360ml
- 広口瓶
『未病を治す薬膳酒』では、25度のホワイトリカーが推奨されていますが、調べによると焼酎(甲類)でOKとのことだったので、今回は焼酎を使用します。
ちなみに、新鮮な黒ごまを使うと風味よく仕上がるらしいのですが、今回は冷蔵庫にあったものを使いました。


手順① 瓶を煮沸消毒する

瓶についた雑菌を殺菌して保存性を増すために、瓶を煮沸消毒します。
鍋にたっぷりの水と、ガラス瓶とふたを入れて火にかけ、沸騰したら弱火で10分ほど煮ます。
煮終わったら瓶を取り出し、乾燥させます。
手順② 瓶を共洗いする

煮沸消毒し、しっかりと乾燥させれば必要ないのですが、乾燥が不十分だったので、今回は「共洗い」という作業もしました。
材料の焼酎を少しだけ瓶に注ぎ、瓶内のガラス面すべてにいきわたるように回転させ、終わったら瓶内の液体を捨てます。
このとき、瓶内に多少の液体が残りますが、気にしなくて大丈夫です。
この「共洗い」は、煮沸消毒ができないような大きい瓶を使うときにも有効な方法です。
手順③ 黒ごまを量る

黒ごまを量ります。
手順④ 黒ごまを炒る

黒ごまを炒っていきます。
このとき、煙が出るくらいまでしっかりと乾煎りするのがポイントだそうです。

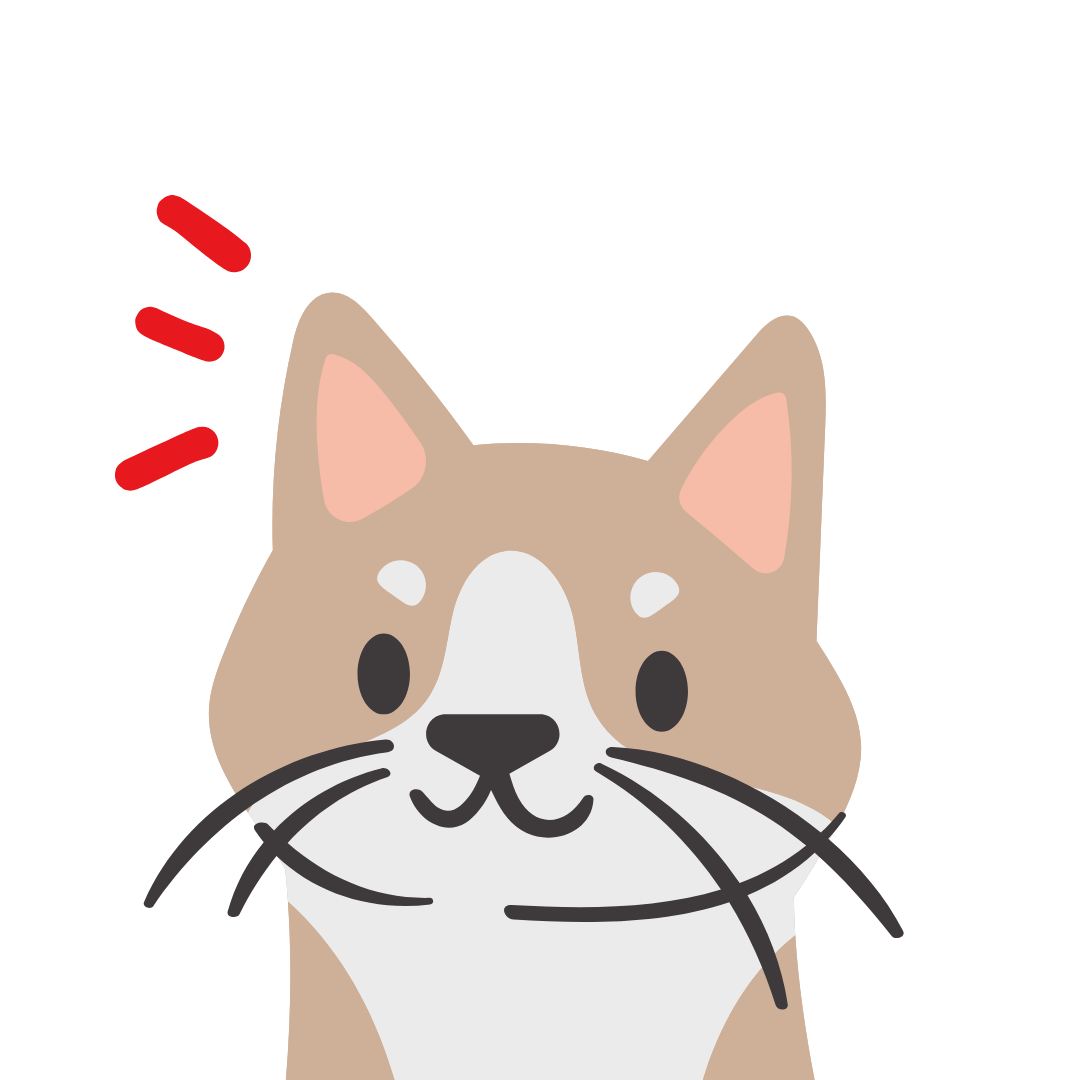
手順⑤ 黒ごまを瓶に入れる

炒った黒ごまの粗熱がとれたら、瓶に入れます。
今回はフライパンを使ったのですが、瓶に入れる作業が意外と難しく、結構な量をこぼしてしまいました。( 不器用なだけという説もあり… )
写真を見ていただくとわかるのですが、テーブルの上に黒ごまが飛び散っています…。
なので、もし注ぎ口付きの小鍋をお持ちの場合は、フライパンではなく、そちらの使用をおすすめします。
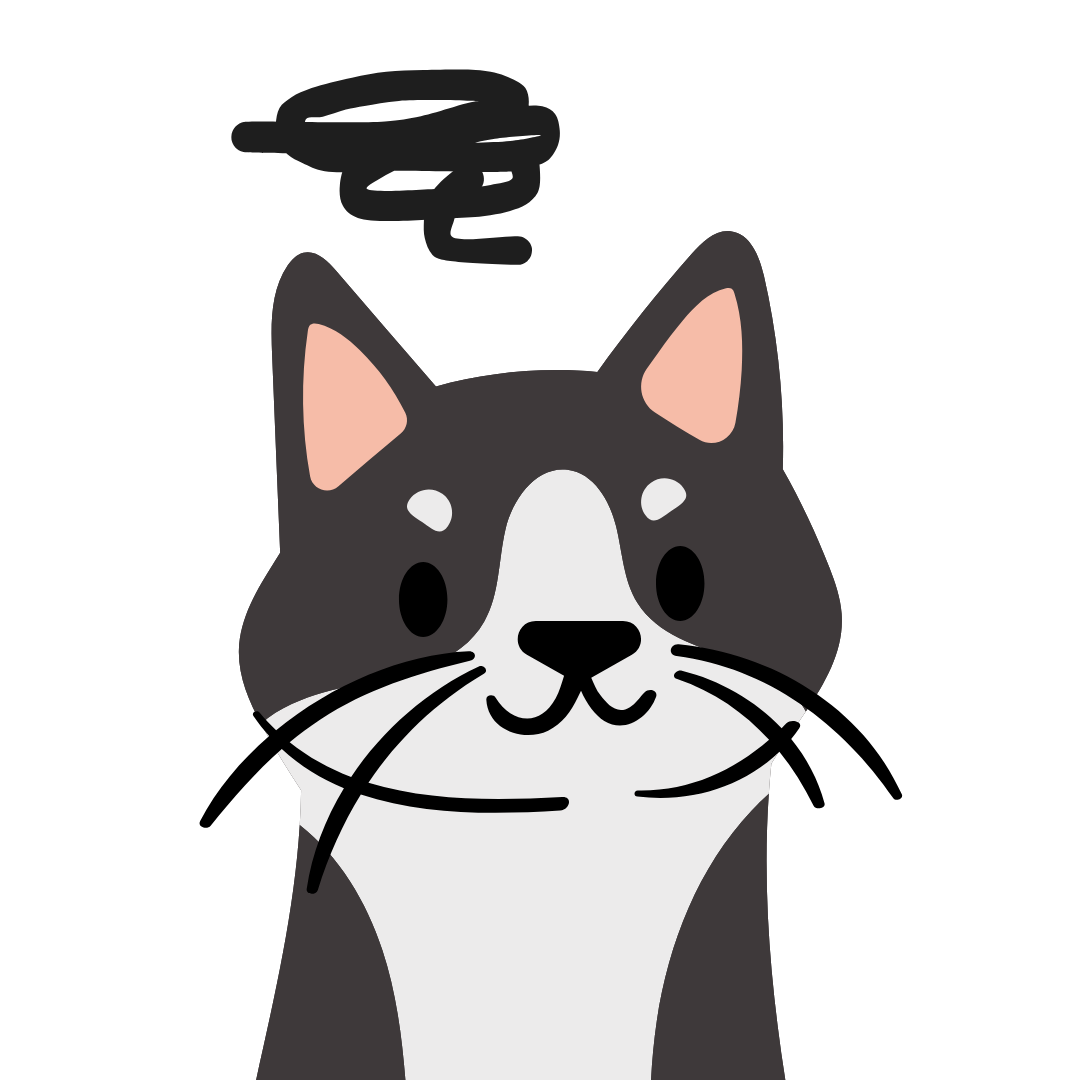
手順⑥ 焼酎を量る

焼酎を計量カップで量ります。
手順⑦ 瓶に焼酎を注ぐ

黒ごまが入った瓶に焼酎を注ぎます。
注ぐときは静かに行うのがポイントだそうです。
手順⑧ ラベルをつける

漬け込んだ材料、日付がわかるように、マスキングテープでラベルをつけました。
これで完成です!

あっという間に焼酎が茶色に変わり、すでに黒ごまが沈みはじめていますね。
『未病を治す薬膳酒』では、冷暗所で2週間以上熟成させたのち、ろ過して細口瓶に移すのが推奨されています。
黒ごまを漬けておくのは3か月が限度だそうです。
漬け込んだ後の様子の変化
せっかくなので、漬けたあとの様子も記録してみました。
1週間後の様子

1週間しか経っていませんが、漬けた直後とは違い、かなり真っ黒になっています。

瓶の底のほうには、ごまが沈殿しています。
よく見ると、黒い皮がはがれて、白ごまのようになっているものもありますね。
2週間後の様子

見た目では、1週間前と大きな変化は感じられません。
黒ごまの成分がしっかりと抽出されているせいなのか、瓶の向こう側は透けて見えないくらい真っ黒です。
3週間後の様子

やはり大きな変化はないようです。
黒ごま酒を飲んでみた感想
熟成期間が3週間過ぎたので、そろそろ飲んでみることにします。
瓶を開けてみると、こんな感じ。

お酒の表面に油が浮いて、ちょっとテカテカしています。
お猪口に注いでみると…

瓶に入っているときよりは薄い色合いで、ほんのり茶色がかっていますね。
香りはというと、ほんのりごまの風味がするかな?という感じ。
すごくいい香りという訳ではないけれど、すごく悪いという訳でもない。
で、肝心のお味はというと、ストレートだとキツイ( アルコール成分が! )。当たり前といえば、当たり前ですね。
そこで、氷を入れて、ロックにしてみました。

焼酎のアルコール分が緩和されて、だいぶ飲みやすくなりました。
香りと同様に、味自体もすごくおいしい!という訳じゃないけれど、飲めないというほど悪くもない。
ごまの風味がほんのりするものの、際立ってコレというクセはなく、薬っぽさもないので、これなら続けられそうです。
漬けるときに砂糖を加えていないのでスッキリとした味わいなんですが、寝る前にちょっと飲むなら少し甘みがあってもよさそうな気もします。

まとめ:韓国ドラマのように、薬膳酒のある暮らし
薬膳酒というと、難しそうに感じるかもしれませんが、身近な材料とシンプルな工程で、こんなに手軽に作れるとは驚きでした。
韓国ドラマに出てくるような「健康と暮らしがつながったシーン」に、少し近づけた気がします。
疲れた体に、ちょっとしたご褒美はいかがでしょうか?
ぜひみなさんも、自家製の薬膳酒を楽しんでみてくださいね。