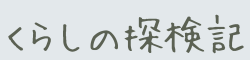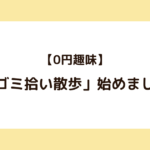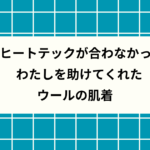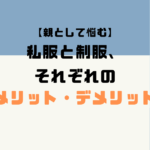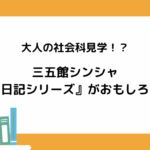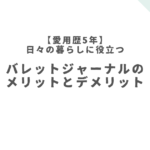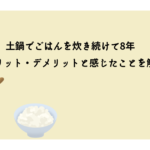わたしの秋の恒例行事といえば、銀杏( ぎんなん )拾い。
ぷっくりとした黄色い実を踏むと臭~い汁が出るアレです。
多くに人に嫌われがちですが、このニオイにも負けず、せっせと拾い集めるのが毎年の楽しみなんです。
なぜかというと、銀杏拾いはお金がかからないうえに、栄養たっぷりのスーパーフードをゲットできるから!
今回は、そんな魅力あふれる銀杏の「拾い方」「下処理」「保存方法」「簡単な食べ方」まで、初心者でも楽しめるように詳しくご紹介します。
この記事のもくじ
銀杏はスーパーフード!?
茶碗蒸しや炊き込みご飯のなかで、脇役というイメージが強い銀杏。
でも実は、栄養価がとても高いんです!
タンパク質やビタミン、ミネラルが豊富に含まれていて、とくにカリウムやパントテン酸、ビタミンCが多いのが特徴です。
薬膳の世界では銀杏は咳を鎮め、痰を切りやすくする働きがあるとされ、漢方薬の咳止め「定喘湯(ていぜんとう)」にも含まれています。
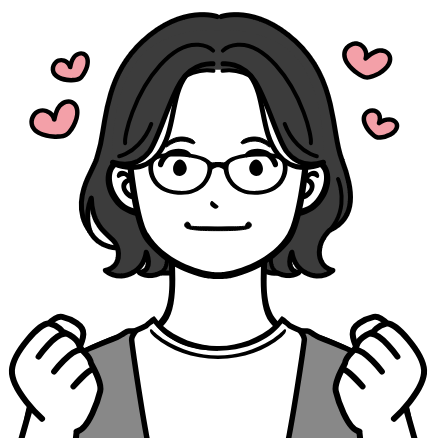

銀杏拾いの時期はいつ?
黄色いイチョウの葉っぱとセットのイメージがある銀杏ですが、イチョウの葉がすべて黄色く変わった後では手遅れ。
地域にもよりますが、9月上旬から11月下旬のあいだがシーズンとなります。
イチョウの葉が黄色く色づきはじめたら銀杏拾いのシーズンに入りますので、銀杏の実の落ち具合をチェックしましょう。
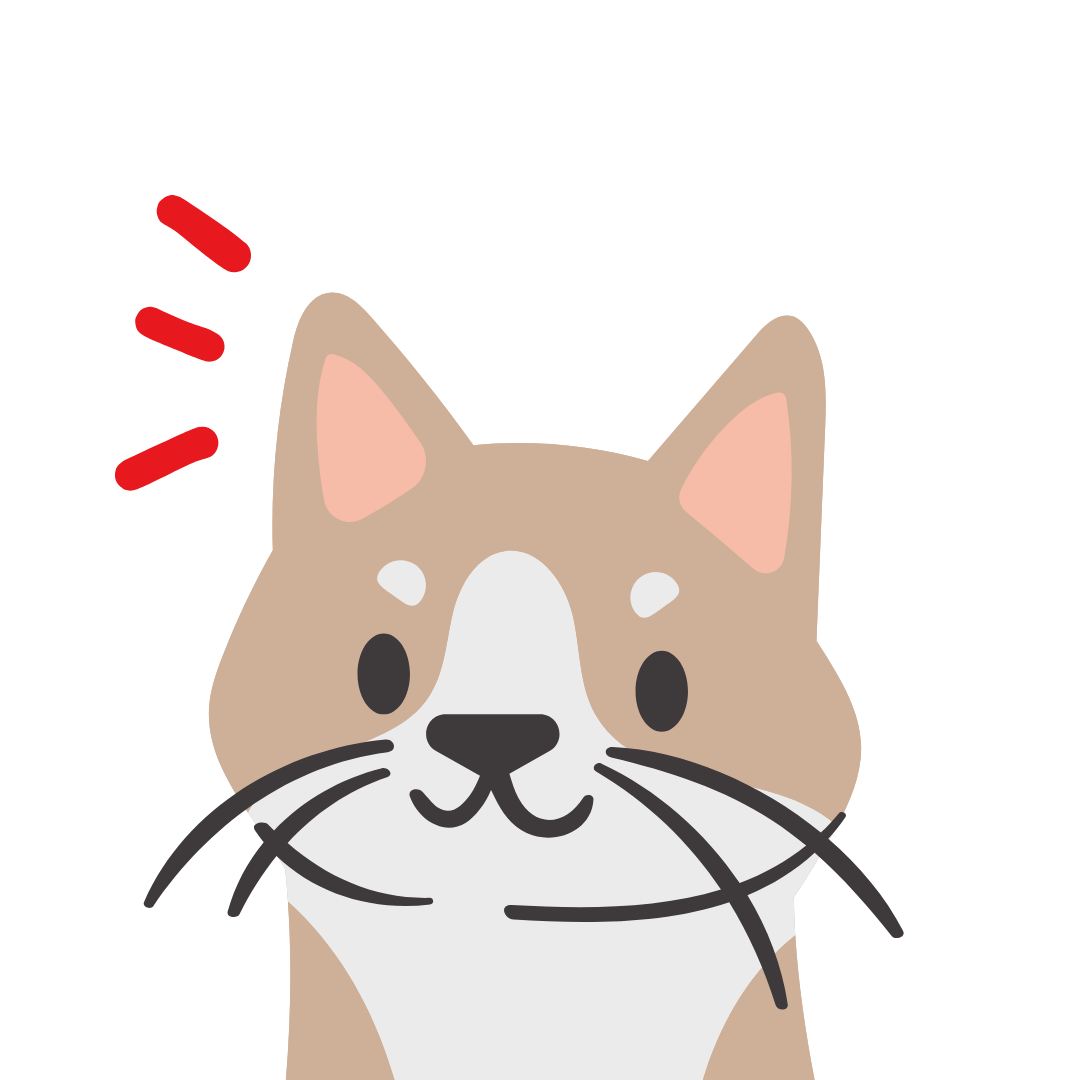
銀杏を拾ってみよう!
銀杏拾いの注意点
銀杏拾いは楽しいレジャーですが、注意しておかなくてはいけないことがあります。
それは、銀杏の実に触れることで「ぎんなん接触性皮膚炎」というかぶれを起こす可能性があることです。
種の周りの黄色いぷっくりとした部分に含まれる「イチオール」という成分が、かゆみ、かぶれを引き起こします。
ですから、銀杏拾いをする場合には、銀杏に肌が接触しないように長袖、長ズボンを身に着け、ゴム手袋かビニール手袋をするようにしましょう。
準備するもの
準備するものは、
- ビニール袋
- ゴム手袋( ビニール手袋 )
です。
ビニール袋だとニオイが漏れて気になるという場合は、ジッパー付き保存袋を使ってもいいですね。
銀杏拾いのコツ
銀杏拾いにとくに難しいスキルは必要ありませんが、覚えておくといいのがこの2つ。
- 自然に落ちている黄色い実を拾う
- なるべく大きなものを拾う
銀杏は、木になっている未熟なものを棒で落としたりするよりも、完熟して自然に落ちたものを拾うのがおすすめです。
柔らかく、熟した実のほうが果肉から種を取り出しやすいので、この後に行う作業が楽に済みます。
未熟な実だと果肉が固いので種の取り出しも大変ですし、実が種にこびりついていて、洗うのも一苦労です。
また、大きな実は中身の種も大きいので、どうせ拾うならばなるべく大きなものを選びましょう。

写真の銀杏のように、つぶれていたり、干からびたりしていても、問題ありません。
ただ、種があるかだけは確認してくださいね。

こんな感じに拾い集めたら、ビニール袋をしっかり縛って、ニオイが漏れないようにして持ち帰りましょう。
電車やバスなどの公共交通機関を利用して持ち帰る場合には、周囲の迷惑にならないよう、ビニール袋を何重かにして包むといいですね。

ついつい夢中になって、取りすぎてしまいます
銀杏の処理方法
拾った銀杏は残念ながらそのままでは食べられません!
黄色い果肉から種を取り出すという作業が必要なんですが、これが臭いですし、大変…。
かなり臭うので外での作業をおすすめしますが、集合住宅などにお住まいの方は近所迷惑にならないようにご注意くださいね。
さて、処理方法はいくつかあるのですが、知り合いの農家さんから教えてもらった方法をわたしは実践しています。

① 果肉から種を取り出す

黄色い果肉から種だけを取り出します。指でぷっくりとした黄色い果肉を挟むと、ツルっと種が出てきます。
取り出した種はザル、もしくはボールに集めていきます。
黄色い果肉は食べられないので、捨てる用のビニール袋に入れましょう。
黄色い果肉が固くて取り出しにくい場合は、ボールに銀杏を入れ、さらに水をたっぷりと入れて、2~3日間放置しておくとふやけて柔らかくなります。
ただ、ニオイのせいでハエなどの虫も寄ってきやすいので、ラップをかけたり、ビニールでくるんで対策しておくのがおすすめです。
種を取り出した様子は、こんな感じになります。

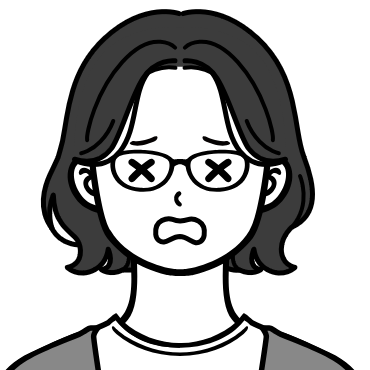

② 種を洗う
種にこびりついている、果肉を丁寧に洗い落していきましょう!
果肉が残っているといつまでも臭うので、しっかりと洗うのが肝心です。
種同士をゴシゴシと擦り合わせるようにすると、効率よく果肉を落とせます。

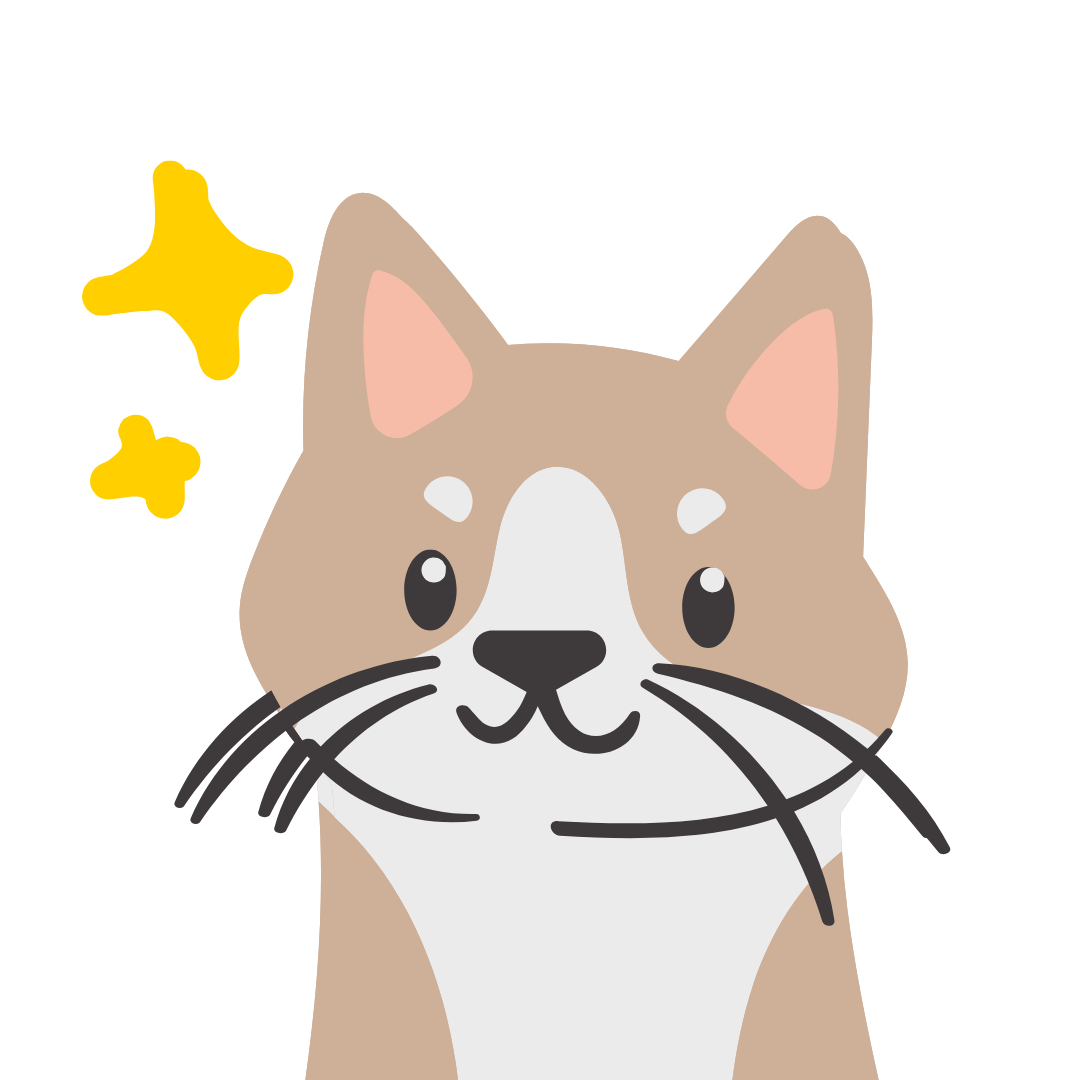
③ 種を乾燥させる
果肉を洗い落としたら、今度は種を乾燥させます。
乾燥が不十分だとカビが生えてしまうので、しっかりと乾燥させましょう。

種の保存方法
ここまで苦労して作業してきた銀杏ですから、大事に食べたいですよね。
そこで大切になってくるのが、保存方法です。
調べたところによると、銀杏の保存方法は常温、冷蔵、冷凍の3種類です。
- 常温:殻付きのまま紙袋に入れるか、新聞紙に包む。保存期間は1週間程度
- 冷蔵:殻付きのままキッチンペーパーや新聞紙に包んで、ポリ袋に入れる。保存期間は1か月程度
- 冷凍:殻をむいて小分けしてラップに包み、フリーザーバックに入れる。保存期間は2〜3か月
わたしの場合は、書類を入れるような大きいサイズの紙封筒に種を入れ、そのまま冷蔵庫の野菜室に入れています。
冷蔵の場合は保存期間1か月というのが一般論のようですが、実際のところ、3~4か月は余裕です。
それを過ぎると、ちょっと実が干からびてきたかなという感じになります。
銀杏の簡単な食べ方
銀杏の手軽に食べたいならば、一番のおすすめはレンジでチンする方法です。
紙の封筒を用意し( 使ってあるものでOK )、そのなかに銀杏に種を入れます。

紙封筒の口を何重かに折り返し、レンジのなかに入れます。

あとは、600Wで20~30秒チンするだけ。
銀杏が弾けて、パンパンという音がしてきたら出来上がりの合図です。

レンジから出してみると、こんな感じで割れ目が入っているので、手で簡単に剥くことができます。

レンチンしても割れ目が入らなかった場合は、種の上にさきほどの紙袋をかぶせ、体重をかけながら手で押せば簡単にヒビが入ります。
わたしは小腹が空いたときに銀杏を5粒ほどレンチンして、コツコツと食べています。

まとめ:銀杏拾いは無料で楽しめる秋の贅沢レジャー!
銀杏拾いはお金もかからず、自然のなかで季節を感じられる楽しいレジャー。
しかも、拾った実は栄養満点で、保存もできるスーパーフードです。
手間は少しかかるけれど、それすらも「秋の風物詩」として楽しんでいます。
まだ銀杏拾いを体験したことがない方も、ぜひ一度チャレンジしてみてくださいね!