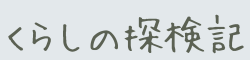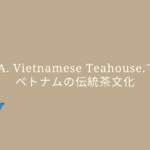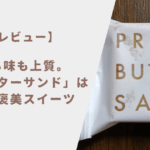庭の片隅や畑のすみに、どこからともなく生えてくるあの雑草、実は食べられるって知っていましたか?
夏になると元気いっぱいに広がる“スベリヒユ”は、見た目こそ地味ですが、栄養たっぷりのスーパーフードなんです。
この記事では、そんなスベリヒユの特徴や見分け方、注意点、そして簡単にできるおひたしレシピをご紹介します。
この記事のもくじ
スベリヒユってどんな植物?

スベリヒユ(学名:Portulaca oleracea)は、夏の畑や庭でよく見かける多肉系の植物。
紫色の茎、濃緑色で肉厚・楕円形の葉、地面を這うように生えている姿は、一度はどこかで目にしたことがあるはず。
繁殖力が旺盛なので厄介者扱いされがちですが、実は食べることができて、しかも栄養満点!
ビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、オメガ3脂肪酸、アミノ酸、食物繊維など、体にいい栄養がいろいろと含まれていますが、オメガ3脂肪酸が豊富なのがとくにポイントです。
若返り成分とも称されるオメガ3脂肪酸を植物のなかでもっとも豊富に含むといわれていて、まさにスーパーフードなんです。
また、中国では「長寿菜」とも呼ばれ、漢方薬の生薬「馬歯莧(ばしけん)」としても重宝されています。
このスベリヒユ、日本ではあまり馴染みのない人のほうが多いかと思いますが、山形県では「ひょう」と呼ばれていて、親しまれているんだとか。
江戸時代、上杉米沢藩が財政困難に陥ったとき、上杉家第9代藩主・上杉鷹山が倹約のために推奨したのがはじまりとされています。
今でもひょう干し( 干したスベリヒユ )はお正月に欠かせない食材なんだそうですよ。

スベリヒユを採るポイント
スベリヒユの採り方
スベリヒユは日当たりのよい、肥沃な土地を好んで生えてきます。採取時期は、夏~秋です。
もし自宅の庭に生えているなら、超ラッキーですね! 草取りのついでに食材も手に入って、いいことづくめ。

コニシキソウはちぎると白い液体がでてくるのが特徴で、葉っぱに紫色の斑紋もあります
採取するときの注意点
スベリヒユは空き地や道路の脇など、いろんな場所に生えていますが、採取する場合には注意点を守るようにしてくださいね。
- 採取しても問題ない場所か確認をしましょう
- 除草剤が使われている場所は避けましょう
- 車通りが多い、排気ガスが気になる場所は避けましょう
スベリヒユのおひたしの作り方

スベリヒユは生でも食べられるのですが、はじめての場合はゆでるのがおすすめ。
ビタミンを考えると生食がいいのかもしれませんが、ゆでたほうが酸味が減って食べやすい味になりますし、スベリヒユに含まれるシュウ酸も減るので、個人的にはゆでが推奨です。
というわけで、一番簡単なスベリヒユのおひたしを作ることにします。
材料
- スベリヒユ 適当
- ポン酢 適当
作り方
1.スベリヒユを洗う

スベリヒユは、地面に近いところに生えているので、結構汚れています。わたしはボールに水をはって、しっかりとつけ洗いします。
ただし、乱暴に洗うと肉厚の葉っぱが傷んでしまうので、やさしく振り洗いするのがおすすめです。
また、この時点で、根っこを手で切りとっておくと後がラク。
根っこも食べられるのですが、硬いのでおひたしには向いていません。
2.スベリヒユをゆでる
鍋に湯を沸かし、沸騰したらスベリヒユを入れ、1~2分ゆでます。

ゆで加減は、すこし茎をかじってみて、スジ感がなければOK。もともと生でも食べられるので、ほどほどゆでれば大丈夫です。
3.水気をしぼり、切る

ゆであがったら水気をしっかりと絞り、食べやすい大きさに切ります。
ちなみに、わたしは横着なので、皿に盛ってからキッチンバサミで切ってます。
4.皿に盛り、ポン酢をかける

皿に盛り、お好みの量のポン酢をかけましょう。麺つゆでもおいしいです。
スベリヒユのおひたしのお味は?
料理ともいえないレベルで、あっという間に完成です。
味の感じとしては、ちょっと酸味のあるモロヘイヤ?とでもいうのでしょうか。少しネバネバとした感じと、茎の少しシャキシャキとした食感があります。
こういう未知な野菜・雑草に抵抗のある夫にも食べさせたのですが、「思ったよりも悪くない」とのことで、肉炒めと一緒に食べておりました。
夏は葉物、青物が不足しがちですが、こういう栄養満点のスーパーフードがその辺で無料で手に入るのはとってもありがたい。
あまり馴染みのない植物だと思いますが、案外おいしいのでぜひチャレンジしてみてくださいね!
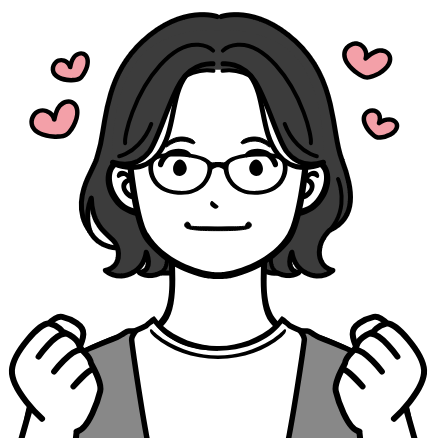
『食べられる草ハンドブック』は季節ごとに植物が分類されているので、初心者さんでも使いやすいですよ