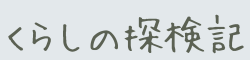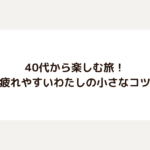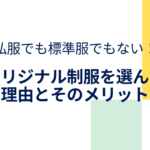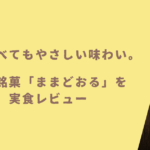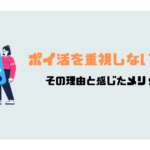「捨て活」「断捨離」「ミニマリスト」といった言葉をよく聞きますよね。
YouTubeには、片付け系・ミニマリスト系の動画がたくさんあり、どれも再生回数が非常に多く、多くの人がこのテーマに関心を寄せているのがわかります。
その中でもとくに人気があるのが、“片付けのプロ”による捨て活動画ではないでしょうか。
プロの手によって、山のようにあったモノがどんどん片付いていき、みるみるうちに部屋がスッキリしていく様子は圧巻。
その光景に思わず見入ってしまいますし、「自分も片付けしようかな」と刺激を受ける人も多いでしょう。
ですが、わたしはいつも気になっていることがあります。
それは、「依頼者はきれいになった部屋を維持できるのか?」ということです。
この記事のもくじ
きれいになった部屋は、維持できているのか?
動画の見どころは、モノがどんどん処分されていく場面。
ですが、そのあと「片付けた人がその状態を維持できているのか?」という点には、あまりスポットが当たりません。
いくら一時的にきれいにしても、時間が経てばモノはまた増え、部屋は元どおり…というのはよくある話。
実際、「片付けられない」という問題の根本にあるのは、モノの量と自分の行動のバランスが取れていないことなのです。

モノを減らす、たった一つの原則
部屋をスッキリさせるために必要なのは、とてもシンプルなこと。
家に入れるモノの量 < 家から出すモノの量
このバランスを継続できなければ、部屋は再びモノで溢れていきます。
そして重要なのは、モノは勝手に家に入ってきたり、勝手に増えたりするわけではないということ。
すべては、住んでいる自分や家族の行動の結果なのです。
この根本を押さえないかぎり、いくら一時的に大金をかけてモノを処分したとしても、元の木阿弥になってしますはずです。

スッキリを維持するための2ステップ
では、具体的に何をすればよいのか? 大切なのは、以下の2ステップです。
① 家にモノを入れるのをやめる
いくら捨て活に励んでも、次から次へとモノが家に入ってきては意味がありません。
ですから、まず優先すべきは「モノの流入を止めること」。
- セールだからといって買わない
- ストックを無駄に買いすぎない
- 衝動買いを控える
ショッピングが好きな人にはつらいかもしれませんが、「必要な物しか買わない」という意識改革が、片付け維持の第一歩です。
どうしても必要な生鮮食料品以外は買わないという気持ちで、徹底して買わないようにします。

② 家の中のモノと向き合う
次にやるべきことは、すでにあるモノを使い切る or 手放すこと。
ただし、ここで注意したいのは「なんでもかんでもとりあえず捨てる」のではなく、自分の行動、暮らしの癖を振り返る時間にすることです。
片付けは、自分を知る作業でもある
たとえば、赤いセーターを手に取ったとします。
- なぜ買ったのか?
→ セールでかわいいと思った。自分へのご褒美。 - どれくらい着たのか?
→ 1回だけ。 - なぜ着なくなったのか?
→ 派手すぎて似合わなかった。合わせる服がなかった。 - なぜ捨てていないのか?
→ もったいない。値段が高かった。
こうして自問自答していくと、自分の“買い物のクセ”や“思考のパターン”が見えてきます。
たとえば、こんな感じでしょうか。
- 衝動買いが多い
- ご褒美の名目で買ってしまう
- 「もったいない」が手放しを妨げている
モノと向き合うことで、こうした行動のクセに気づくことができるのです。
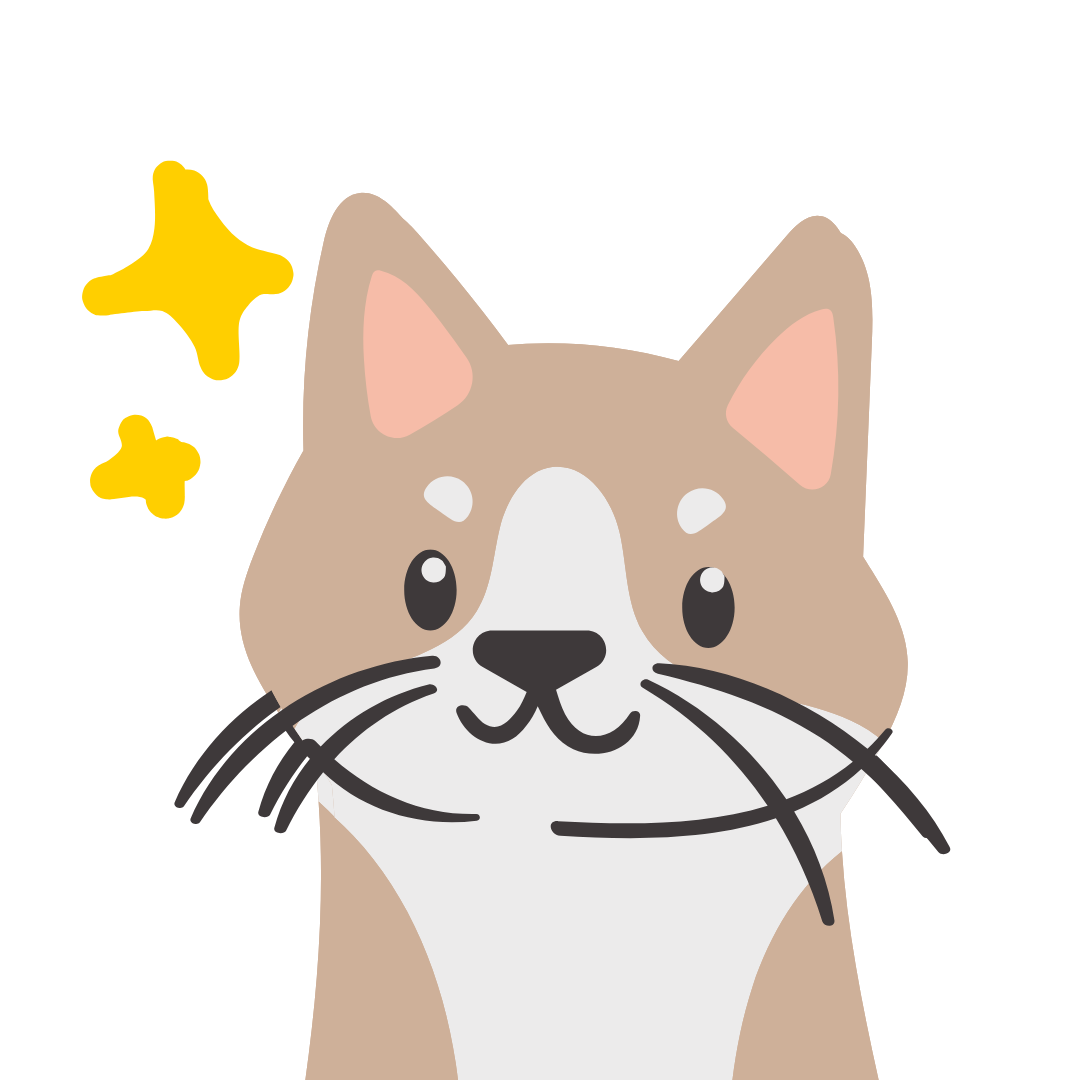
捨て活の本当の意味とは?
ただ闇雲にモノを捨てる「捨て活」は、実は根本解決になっていないことが多いです。
それよりも大切なのは、「なぜそのモノが家にあるのか」を振り返り、自分の行動・思考のクセと向き合うこと。
家の中にあるモノは、自分の人生・行動・選択の積み重ね。
それらと真剣に向き合うことで、初めて本当に「モノに振り回されない暮らし」へと一歩踏み出せるのです。
まとめ:片付けは自分との対話
プロに頼んで一気に片付けるのもいいかもしれません。
けれど、本当に大切なのは「自分自身の行動を変えること」。
捨て活とは、ただの「モノの整理」ではなく、自分の暮らしを見つめ直す時間でもあります。
片付けのその先にある、本当に自分らしい暮らしを手に入れるために、今日も、モノと、そして自分自身と向き合っていきませんか?
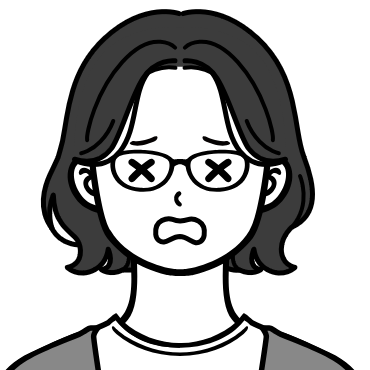
心配性、先回りでモノを買ってしまうので、最近は「必要になるまで買わない」と自分に言い聞かせています