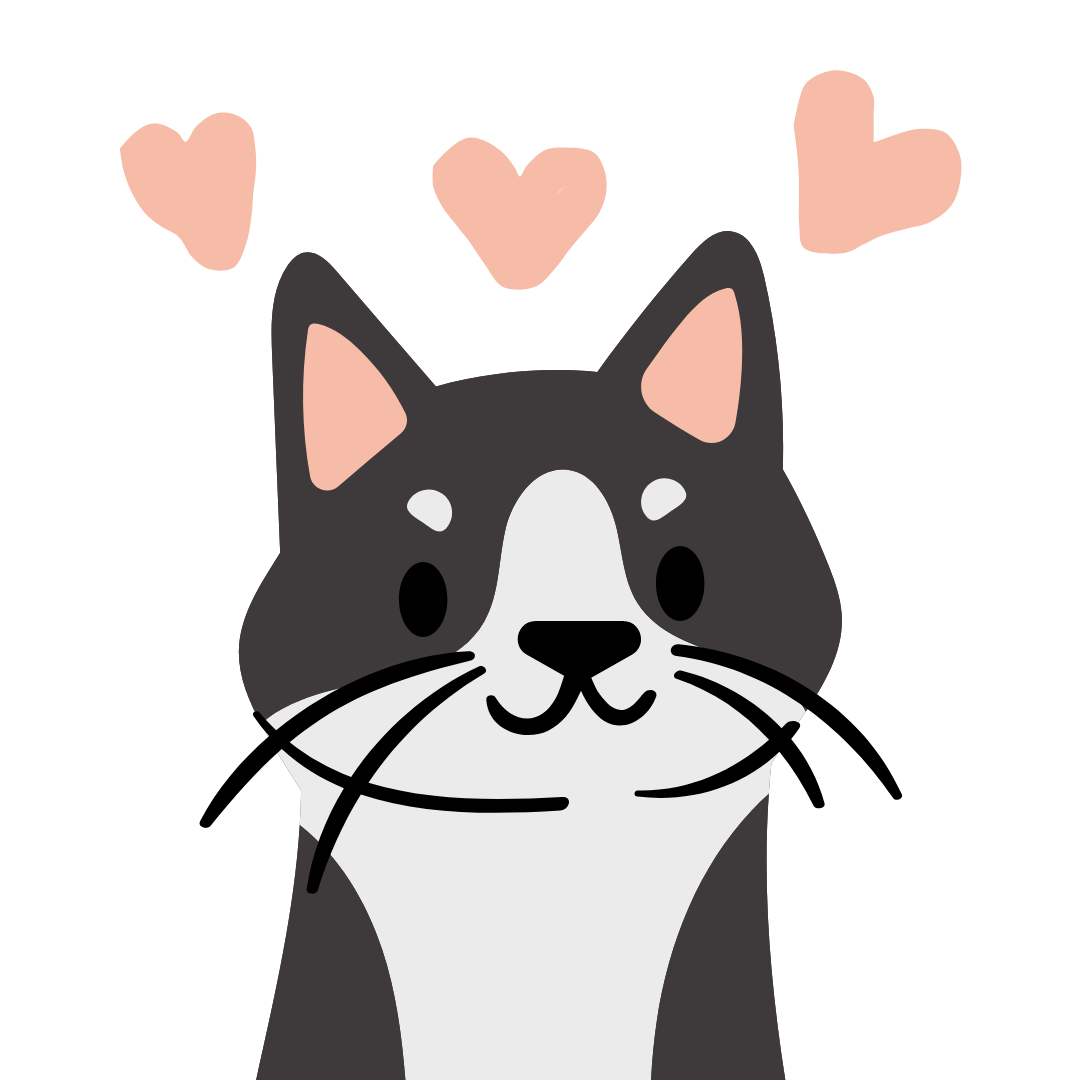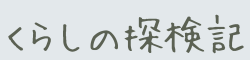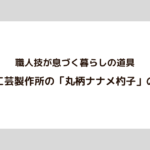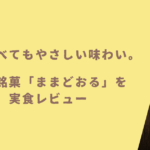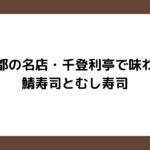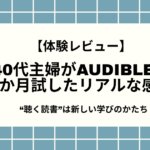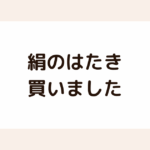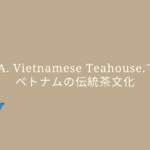仕事に子育てに追われる日々、忙しさの中でも食事の時間は大切にしたいものです。
そんな日常に、ほんの少しの心地よさをプラスしてくれるのが、神奈川県小田原市の職人たちが手掛ける木の器——薗部産業の「めいぼく椀」です。
1949年に創業し、70年以上にわたり一貫生産にこだわり続ける薗部産業。
小田原の風土に根ざした木取り・乾燥・ろくろ加工・ウレタン塗装まで自社で手がけるからこそ生まれる、手にすっと馴染む滑らかな曲線と、美しい木目の“唯一無二感”が魅力です。
この記事では、10年以上愛用しているわたしが感じるめいぼく椀の魅力を、実際の使用感とともにご紹介します。
この記事のもくじ
薗部産業はどんな会社?
薗部産業は神奈川県小田原市にある、1949年(昭和24年)創業の木製食器メーカー。
国産材や海外の良質な木材を用い、製材から乾燥、木地挽き、塗装、漆塗りまで一貫して自社で手掛けるこだわりがポイントです。
「つくりたいモノ/つくれるモノをつくる」
ではなく
「愉しい食卓をもっと愉しく」
でつくるモノづくり
をコンセプトに、日々、職人さんたちが製作に励んでおられます。
薗部産業の「めいぼく椀」の魅力
愛用歴10年を超えるわたしが考える、めいぼく椀の魅力は
- 魅力① 和にも洋にも使えるシンプルさ
- 魅力② 美しい木目の唯一無二の器
- 魅力③ 木製品なのにお手入れ簡単
- 魅力④ 丈夫で長持ち!
- 魅力⑤ 日本の造林業を支えるモノづくり
です。
それぞれ詳しくお話していきますね。
魅力① 和にも洋にも使えるシンプルさ
わたしがめいぼく椀に惚れた最大の理由は、なんといっても無駄のないシンプルなデザイン。
日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨のしくみである、グッドデザイン賞を1996年に受賞。さらに、2021年にはロングライフデザイン賞を受賞したのも納得です。
飾り気がなく、ただただシンプルなので、どんな料理にも合わせやすい。
ですから、わが家では、和洋中問わず、さらにはデザートにと毎日毎食大活躍です。
定番のお味噌汁はもちろん、
ある日にはシチュー皿として、
ある日には鍋料理の取り皿として、
ある日には素麺やそばの麺つゆ入れるお椀として、
ある日にはアイスクリームを盛る器として。
めいぼく椀を丸一日使わない日というのは買ってからないんじゃないかと思うほど、フル活用しています。
絵付けがしてある器も素敵ですが、絵柄によって盛り付ける料理ってどうしてもイメージが左右されてしまいますよね。
でも、めいぼく椀は一切の装飾がないので、どんな料理でもすんなりと受け入れる懐の深さがあるのです。
また、めいぼく椀は持ったときの手への馴染みやすさが素晴らしいんです。まさに、しっくりという言葉がふさわしい。

器の微妙なカーブは手への当たりもやさしく、木の温かみがふわっと伝わってくるのは、さすがデザインから作製まで一貫して自社にこだわっている賜物ですよね。
シンプルでありながらも、使う人をしっかりと考えているのが実感できます。
めいぼく椀を買うまではテキトーな安いお椀を使っていたのですが、こんなにも器によって違いがあるのかとびっくりしたのを今でも覚えています。
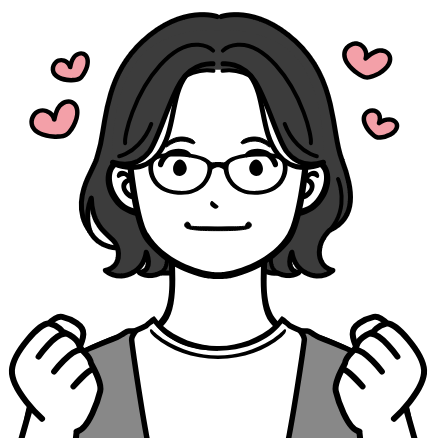
魅力② 美しい木目の唯一無二の器
めいぼく椀はの魅力で外せないのは、その美しい木目。
日常生活での利便性を考えて塗装はしてあるのですが、自然のままの木の色、模様を存分に味わえます。

めいぼく椀に使われている木は6種類あり、
- サクラ:ほんのり赤みを帯びた色味
- ケヤキ:黄味がかった色、力強くダイナミックに走る木目
- ブナ:ナチュラルな印象でやさしい木目
- クルミ:茶色が深く落ち着いた雰囲気
- クリ:大きな木目が表情豊かな褐色の木肌
- ナラ:落ち着いた少しグレイッシュな色味
と、それぞれ特徴があります。
どの木も個性があって素敵ですが、木目そのものを活かしたデザインなので、たとえ同じ木の器でもどれ一つとして同じ模様のものはなく、それぞれが唯一無二の器なのです。

左側から、ナラ、ブナ、ヌルデ。(現在、ヌルデは生産されていません)


また、めいぼく椀は経年変化も素敵。
わが家では10年以上使ってきて、どの器も買ったときよりも少しずつ濃くなり、傷もつき、ヒビが入ったりしてきましたが、それも味わい。
これがプラスチック製品だとこうはいきませんよね。
使い込むほどに味が出て愛着が湧いてくるのは、天然製品だからこその贅沢です。

魅力③ 木製品なのにお手入れ簡単
木製品って、使うのに少しハードルが高いイメージがありますよね。
特別なお手入れが必要となると、「そんなの無理、無理」と毎日忙しい身では敬遠してしまうのも当然の話です。
そんな忙しい現代人のニーズにも応えてくれているのが、薗部産業のモノづくりマインド。
食卓に木を取り入れている人のうち
どれだけの方が毎日お手入れできるでしょうか使うたびにお手入れが必要な うつわ を
気軽につかうことができるでしょうか
「ずっと使う」にとって「気軽さ」はとても大切なコト
私たちは
小田原の伝統的な技法「すり漆」 と
薗部産業/クラフト木の実が創業以来
養ってきた「ウレタン塗装」 で
そんな「気軽さ」を
引用:薗部産業
この「気軽さ」を出すために、めいぼく椀にはウレタン塗装がしてあります。そのおかげで、“特別なお手入れ”は不要。
もちろん、水に一晩漬けっぱなしみたいなのはNGですが、普通に洗剤をつけたスポンジで洗っても大丈夫。
“ちょっとだけ丁寧な気持ち”で扱ってあげるだけで、ほかに特別なことはなにもないのです。
「気軽さ」のおかげで、子育てにバタバタと追われていたこの10年でも、めいぼく椀はなんの無理もなく使え、わが家の日常に溶け込んでくれました。
本格的な木の器なのに、手入れは気負わず、気軽に。
まさに現代人のライフスタイルにマッチしているのが、めいぼく椀なのです。
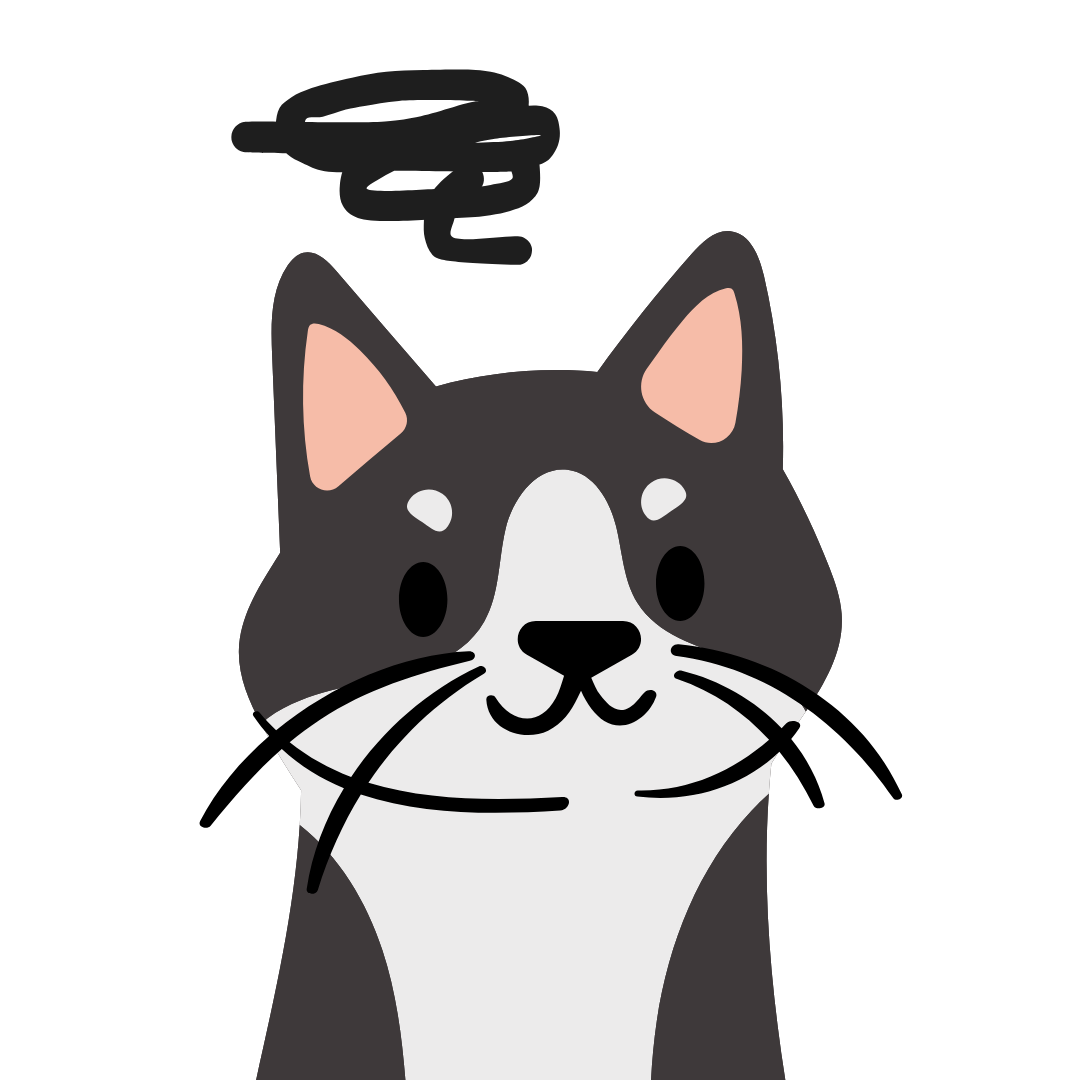
魅力④ 丈夫で長持ち!
わが家でめいぼく椀を使うようになってから、もう13年。でも、まだまだ現役です。

もちろん、よく見れば傷もヒビもあるし、お椀の形も少しゆがみが出てきているけれど、ふだんの食卓には何の支障もありません。
まさに、10年、20年愛せる耐久性、使いやすさ、美しさを兼ね備えているめいぼく椀は、“一生もの”というフレーズも過言ではないかもしれませんね。
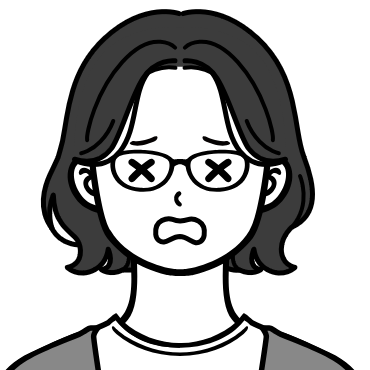
丈夫ではあるけれど、やっぱり丁寧な扱いは必須ですね
息子は食器の扱いが雑なので、めいぼく椀はとりあえずお預け状態です
魅力⑤ 日本の造林業を支えるモノづくり
サクラ カエデ ケヤキ ブナ クリ クルミ ナラ
日本の 豊富な水 と たくましい大地 で
育った木々
森から届いた大切な素材
私たちはそれを受けとり
モノを生みだしています
引用:薗部産業
薗部産業では、ウォールナット、メープル、チェリー、ビーチ以外の木材は日本産にこだわっています。
めいぼく椀に使われている木材も日本産。
海外からの安価な木材を使えば安く大量生産できるかもしれないけれど、それではいずれ日本の豊かな自然は失われてしまいます。
日本で育った木でモノづくりをする職人さんたちがいて、それをわたし達一人一人が少しでも生活に取り入れれば、日本の大切な自然を守っていくことにつながるはずです。

いですよね
まとめ:めいぼく椀は日常を豊かにする器
100円ショップでもお椀が手に入ることを考えると、4,000円ほどするめいぼく椀は正直、お安い買い物でありません。
でも、10年経ってわかったのは、めいぼく椀は全然高くはなかった!ということ。
4,000円程度で10年以上使え、特別なメンテナンスも不要。1年あたり400円でこの暮らしの豊かさが手に入るのであれば、むしろ安いとさえ今では思っています。
毎日、仕事に家事、育児にと、時間に追われる日々であっても、ふと、食卓に「ちょっとした心地よさ」があるというのは贅沢なものです。
わが家にとって、めいぼく椀は、使うたびに愛着が湧き、暮らしに寄り添い続けてくれるパートナー。今のお椀がダメになってしまっても、まためいぼく椀を選びたいと思っています。
もし長く愛せる器をお探しでしたら、めいぼく椀を候補に入れてみてはいかがでしょうか。