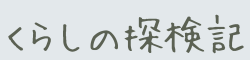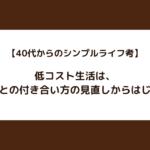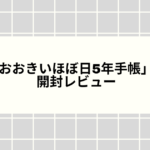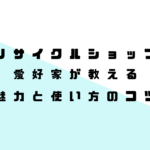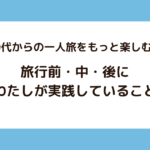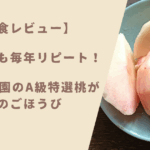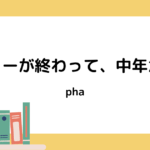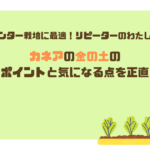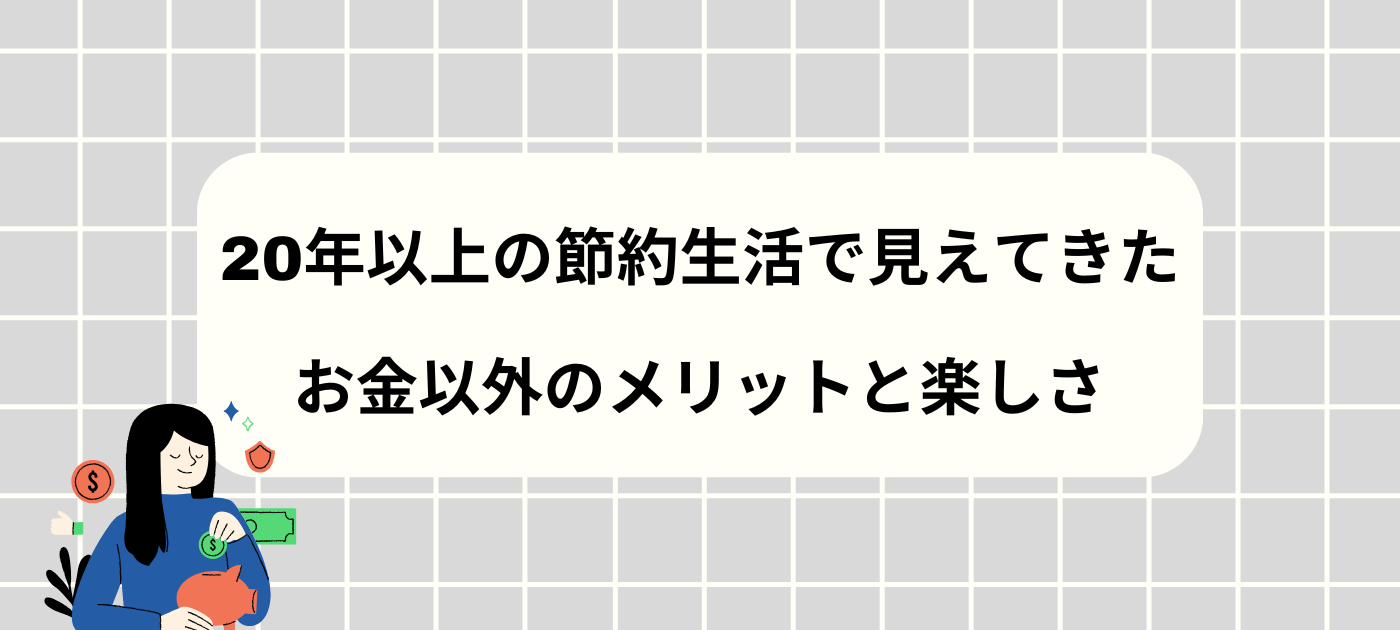
今、節約が世間的に注目されています。物価の上昇が止まらず、その一方で給与所得は伸び悩んでいて、家計が苦しいと感じる人が増えているようです。
もちろん、我が家もそれは同じ。でも、我が家はず~っと節約生活をしているので、正直なところ、今以上の節約をすれば生活のクオリティが下がりすぎてしまうため、これ以上はなかなかできないのが厳しいところです。
さて、この記事では、学生時代から節約生活を始め、その期間も含めれば20年以上も節約生活を送っているわたしが考える節約のメリットや楽しさについてお話しします。
この記事のもくじ
節約とは?
わたし達は、節約、節約とよく言いますが、節約の定義って何だろうと改めて思い、Wikipediaで調べてみました。
Wikipediaによる定義は次のとおりです。
節約あるいは倹約とは、無駄遣いを極力なくすように努めること。
行動科学においては、より長期的な目標を達成するために、抑制して財を取得するその傾向および都合をつけながら既得財を利用することと定義されている。
世間で思っているイメージそのまんまという感じですね。
個人的に興味深いのは、「都合をつけながら既得財を利用すること」という部分。すでに自分が持っている財産、資源を利用するのも立派な節約であるという定義なんですね。
節約家が考える節約のメリット
世間一般では嫌われ者の節約ですが、人生の大半を節約しながら暮らしてるわたしには節約が人生そのものという感じです。
ですから、暮らしと節約が同義な感じで、正直なところマイナスなイメージはほとんどなく、それどころか、楽しんでいるといってもいいかもしれません。
そんな筋金入りの節約家であるわたしが考える節約のお金以外のメリットを挙げてみたいと思います。
スキルが上がる
節約のメリットとして筆頭にあがるのは、まずこの「スキルが上がる」ではないでしょうか。
節約を意識すると、お金を使って外注するという選択肢をなくし、自分でできることは自分でなんとかするというスタンスで生活することになります。
たとえば、料理。
コンビニ、ファストフード、ファミレスのようなお手軽飲食から、もう少しちゃんとした食堂やレストランまで、お金を払えば食べ物の自分の代わりに作って出してくれるサービスは至るところにあります。
でも、三度三度の食事を外注していてはお金を貯めるのは難しいので、節約しようとすると外食ではなく自炊をする必要があります。
最初はご飯を炊く、パンを焼くくらいしかできなくても、少しずつ内容をレベルアップしながら続けていればスキルは上がってくるもの。
料理スキルが上がれば、高いお金を払って外食する必要性はなくなりますし、その一方で外食した際にはそのありがたみもわかるようになり一石二鳥です。
我が家の夫は料理をするのですが、どんどんと腕を上げ、今では魚をさばくのが楽しみになっています。
新鮮な魚を丸々1匹買えば、身の部分はお刺身にして、あらの部分はおみそ汁にと、魚尽くし料理の出来上がり。外食をすれば1人分にもならない値段で、家族4人が食事を楽しめます。
さらに趣味の料理が発展し、今では包丁を研いだりもするようになり、スキルがどんどんと広がっています。
このような感じで、お金を使って人に頼むのではなく自分で行動するようになると、スキルは自然と身についていくのです。
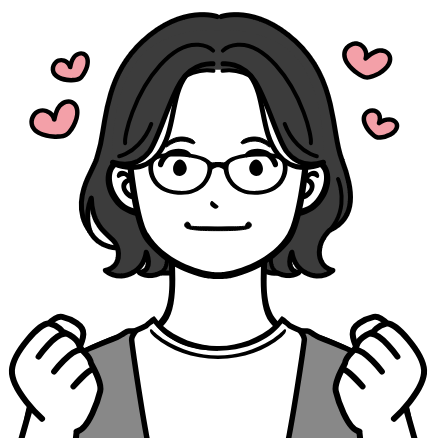
余計に働かなくていい
節約には労働と同じ価値があります。
しかも労働とは違い、それほど個人の能力差がなく、かつ再現性が高いという点においても、労働よりも節約のほうが簡単です。社会的能力の低いわたしでも継続できているのがその証拠。
節約とは自分が働いて家計からのお金の流出を減らす行為ですが、節約をしない場合にはお金を払って自分以外の人に働いてもらう必要があります。
となると、人にお金を払うために余計にお金を稼がなくてはいけません。
お金を稼ぐ能力が高い人は、自分の時間を使って節約をちまちまするよりも働くほうが合理的でしょう。しかし、そうでない人間の場合には、節約のほうが圧倒的に簡単です。
また、どんどんと蓄財したい人は別ですが、そこまで目指さないのであれば、節約して浮いたお金の分は働く時間を減らすという選択も可能です。
これはライフスタイルにもよりますが、節約によって働く時間を減らすことができ、自分の自由時間を生み出すこともできるのです。

自己肯定感が上がる
節約は地味な活動です。一朝一夕にどうこうできるものではなく、淡々、コツコツと積み重ねることで初めて成果がみられるものです。
しかも、ひとつひとつの行動も地味。SNS映えするような行為はまったくありません。
でも、その地味な行為を諦めることなく継続できたという達成感は何ものにも代えがたいのではないかと、わたしは思っています。
世間映えはしなくとも、少しずつお金やスキルが増えていくにつれ、「自分でもここまでできた」と実感できるようになります。
自己肯定感が高まると、さらに頑張ろうという気持ちが湧いてくるので、ここまで到達できればあとはいいサイクルが自動的にグルグルと回っていきます。図にするとこんな感じです。
頑張る
↓
目標達成
↓
自己肯定感アップ
↓
さらに頑張る
↓
さらに高い目標達成
↓
自己肯定感さらにアップ
↓
図を書いていて受験勉強を思い出したんですが、節約もまったく同じ。最初は手探りで、目標到達までは遥か遠い道のりに感じますが、やればやれるものなんですよね。
この過程で培われる自己肯定感は目には見えないけれど、大きなメリットだと思います。

創意工夫をするようになる
節約を意識するならば、何でもお金で解決するのはご法度になります。お金さえ払えば簡単に解決できるのはわかってはいるけれど、自分のスキルと時間を使ってどうにかしなくてはいけません。
そこで求められてくるのが、創意工夫をする能力です。
また料理の例を出しますが、たとえば肉じゃがをつくるとしましょう。
自分が興味をもったレシピの材料は
- じゃがいも
- 玉ねぎ
- にんじん
- いんげん
- 牛肉
だったとします。そこで何も考えなければ、そのままレシピ通りの材料を買ってきてつくりますよね。
ですが、節約道ではこれではダメ。ちょっと頭をひねらなくてはいけません。
レシピを見て、
牛肉はお値段的に厳しいから、豚肉で代用できないかな
いんげんは旬の季節じゃないから、安くなっている絹さやにしよう
みたいな感じで、自分の頭で考えて応用するのが肝心です。
何事もはじめはレシピやマニュアル、アドバイスに従ったほうが楽ですが、ずっとそのままでは進歩がありません。自分に合うようにカスタマイズしてこそです。
節約は金銭的制限があるからこそ、自然と創意工夫をするようになり、脳にもいい刺激になるのです。
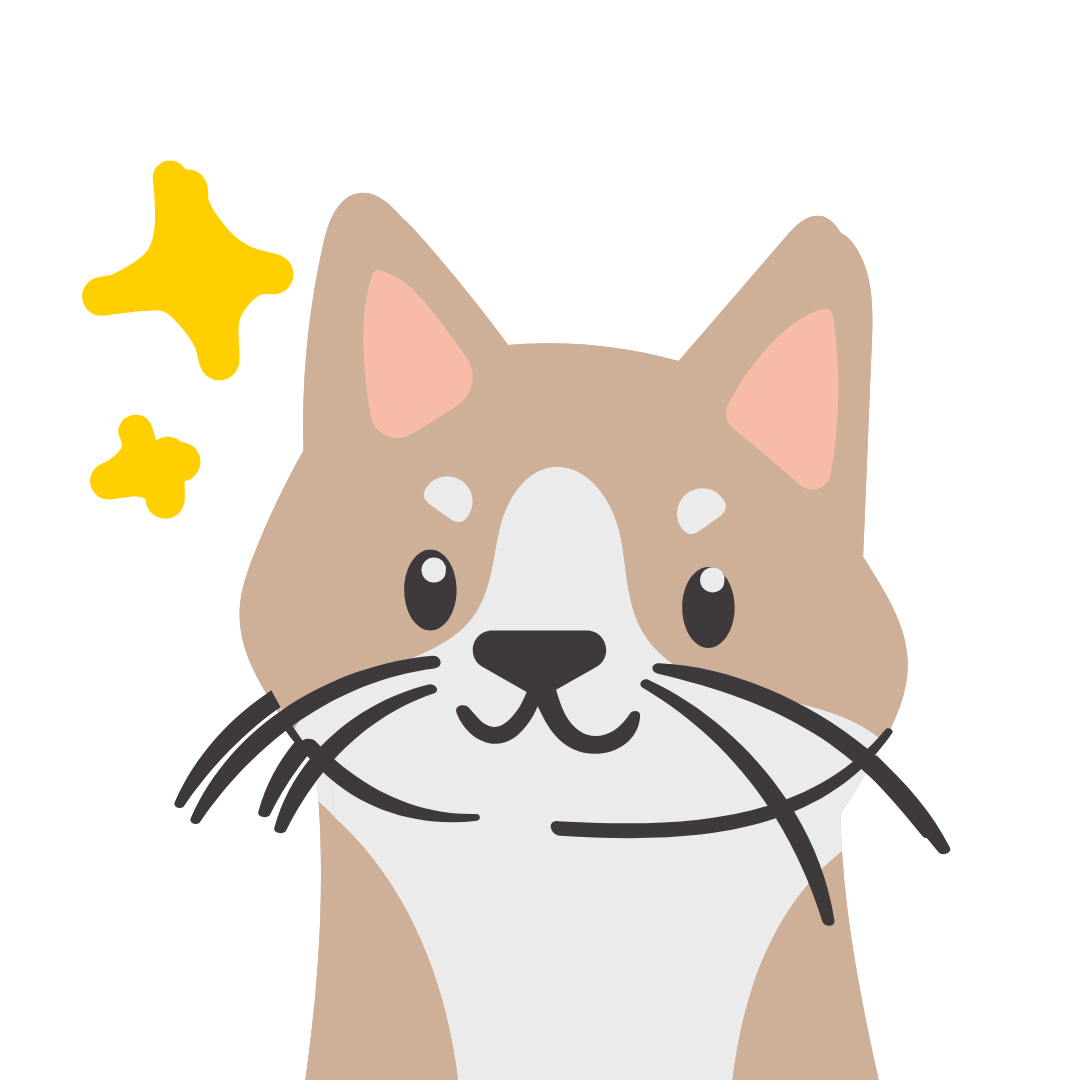
環境に優しい
「捨て活」や「ミニマリスト」というワードは、モノにあふれた日本においてはもはや定着したといえるでしょう。
YouTubeでも、捨て活の動画は再生回数が多く、人々の関心が高いのがよくわかります。
モノを処分してキレイな暮らしをするのは大いに結構ですが、また新たにモノを買いなおすのでは節約という観点からは意味がありません。
どうにもならない、いわゆるゴミは処分したうえでの話ですが、節約するためには残ったモノは使い倒さなくてはいけないのです。
わたしもなるべくすっきりした生活を送るために不用品は努めて処分しますが、基本的にモノはできるだけ長く使うことを心がけています。
たとえば、セーターをひっかけて穴が空いてもニードルパンチで補修をして着続けたり、傷んだタオルは雑巾にして使ったりと、最後まで使い切る努力をします。
これらの努力はお財布にも優しいですが、結果のところ環境にも優しいのが嬉しいところ。大げさな活動をしなくとも、日常生活から環境問題に貢献できるのです。

まとめ
一般的に、節約は惨め、貧しいなどネガティブなイメージを抱かれがちですが、実は金銭以外にもメリットがいっぱいです。
景気がいいとはいえない日本においては、節約をせざるを得ない人はますます増えていくことでしょう。
節約ををツラいと感じるか、楽しいと感じるかは自分次第です。どうせやるなら楽しまないと損だとは思いませんか?
節約が嫌で仕方がない人も多いかと思いますが、節約にも楽しい面があるのだと知ってもらえると嬉しいです。